公的制度の「理想と現実」~住宅セーフティネット編~
※本記事は、2025年10月施行の「改正住宅セーフティネット法」にあわせて内容を更新しました。
(初回公開:2025年7月9日/最終更新:2025年10月14日)
空き家は増え続けているのに、高齢者が入居できない。
2025年10月の法改正で「居住サポート住宅」などの新制度が始まりましたが、実際の現場では“住まわせない自由”がいまだに残っています。
今回の記事では、改正後の住宅セーフティネット制度の仕組みと、それでも変わらない現実、「高齢者は入れません」という壁の正体を整理します。
はじめに:家は余っているのに、借りられない現実
日本には今、約900万戸の空き家があります。
それなのに「高齢者お断り」の賃貸が、当たり前のように存在している。
働き抜いてきた世代が、老後に住む場所さえ選べない矛盾をどう説明すればいいのでしょうか。
制度の理想:誰もが安心して暮らせる社会へ
住宅セーフティネット制度は、高齢者や低所得者、障がい者など住宅確保が困難な人々のために設けられた仕組みです。
大家が「要配慮者の入居を拒まない住宅」として物件を登録すると、改修費補助などのインセンティブが受けられます。
つまり本来は、貸す人・借りる人の双方が安心できる制度のはずでした。
検索してみた現実:理想とはほど遠い「2件」
私は実際に、国交省の「セーフティネット住宅 情報提供システム」で物件を検索してみました。
検索条件は、下記の通りとしました。
- 神奈川県横須賀市、三浦市
- 家賃:5万円以下
- 入居対象者:低額所得者、高齢者
- 間取り:1k/1DK/1LDK
- 部屋状況:空室、部屋状況についてはお問合せ下さい
結果、ヒットしたのはわずか2件。築40年以上、1K・20㎡前後の物件でした。
家賃は3〜4万円台と安いものの、設備や環境は古く、三浦市では該当物件ゼロ。
理想とはほど遠い現実。これが、全国登録94万戸という数字の中身です。
保証人問題に絞って検索してみると
大家さんが高齢単身者に対するリスクの一つとして、保証人問題を抱えていることは、前回の記事でも触れました。
では、連帯保証人や家賃保証加入が不要な物件に絞って検索したら、どうなるでしょうか?
先ほどの詳細条件の一つとして、連帯保証人および家賃保証加入 不要を条件に全国で検索してみました。
全国の総登録件数 127,437件 総登録戸数 953,541件中、該当したのは、7棟 70戸 のみでした。
しかも全て1R、9.32㎡ほど(6畳)の部屋で、キッチンやトイレ・バスなどの設備は共用だったりしました。
何か思っていた理想の老後生活との乖離に絶望すら覚えます。
データで見る矛盾:空き家は900万戸なのに
総務省の最新調査(令和5年住宅・土地統計)によると、全国の空き家は約900万戸(空き家率13.8%)。
2018年から5年でさらに51万戸増えました。
ところが、セーフティネット住宅の登録数は900万戸のうち1割にも満たず、実際に高齢者が住める物件はさらに限られています。
落とし穴①:大家の「選別権」が残ったまま
最大の問題は、制度設計そのものにあります。
セーフティネット住宅を登録する際、大家は「どの要配慮者を受け入れるか」を選べるのです。
つまり、
- 外国人はOK、高齢者はNG
- 子育て世帯はOK、障がい者はNG
といった設定が合法的に可能。
表向きは「拒まない住宅」でも、実際は誰を拒まないかを選べる仕組み。
これでは、最も住まいに困っている高齢単身者が弾かれてしまうのも当然です。
落とし穴②:大家が抱えるリスクと不安
大家の側にも事情はあります。
孤独死による損害リスク、家賃滞納の懸念、緊急時の対応先がない。
この3つの不安が、「高齢者は避けたい」という心理を強くしています。
補助金や制度だけでは、その不安を解消できません。
2025年10月の改正:制度はどう変わった?
今回の改正では、次の3点が大きなポイントです。
- 居住サポート住宅の創設: 大家と居住支援法人が連携し、見守り・安否確認・生活支援を行う仕組み。
- 認定家賃保証制度: 国が基準を満たす保証会社を認定。要配慮者の保証を断らない、緊急連絡先を親族に限定しないなど。
- 終身建物賃貸借の手続き簡略化: 借主が亡くなると自動で契約終了。大家の負担を減らし、借主も「生涯住める安心」を得られる。
一見すると、貸しやすくする方向での前進です。
しかし・・・・・「住まわせない自由」は残った
ここが核心です。今回の改正でも、大家の選別権そのものは変わっていません。
制度の目的は「誰もが住める社会」ですが、実際には「貸す側が安心できる社会」に寄っています。
居住サポート住宅で見守りは強化された。
終身契約でトラブルは減った。
でも、そもそも「高齢者は入れません」と言われたら、何も始まらないのです。
まとめ:制度は進んだ。でも、人の壁は残った
- 空き家900万戸、セーフティネット住宅は約94万戸。
- 大家の選別権は今回も維持された。
- 改正は「貸す安心」を整えたが、「借りる希望」までは届いていない。
- 真のセーフティネットには、人を排除しない設計が不可欠。
老後の住まいについて、こちらのカテゴリーで考察しています。
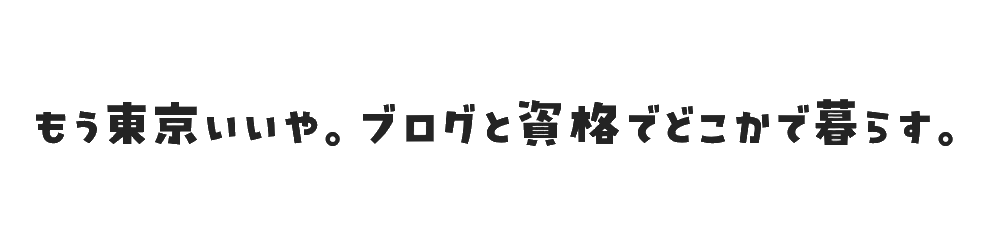
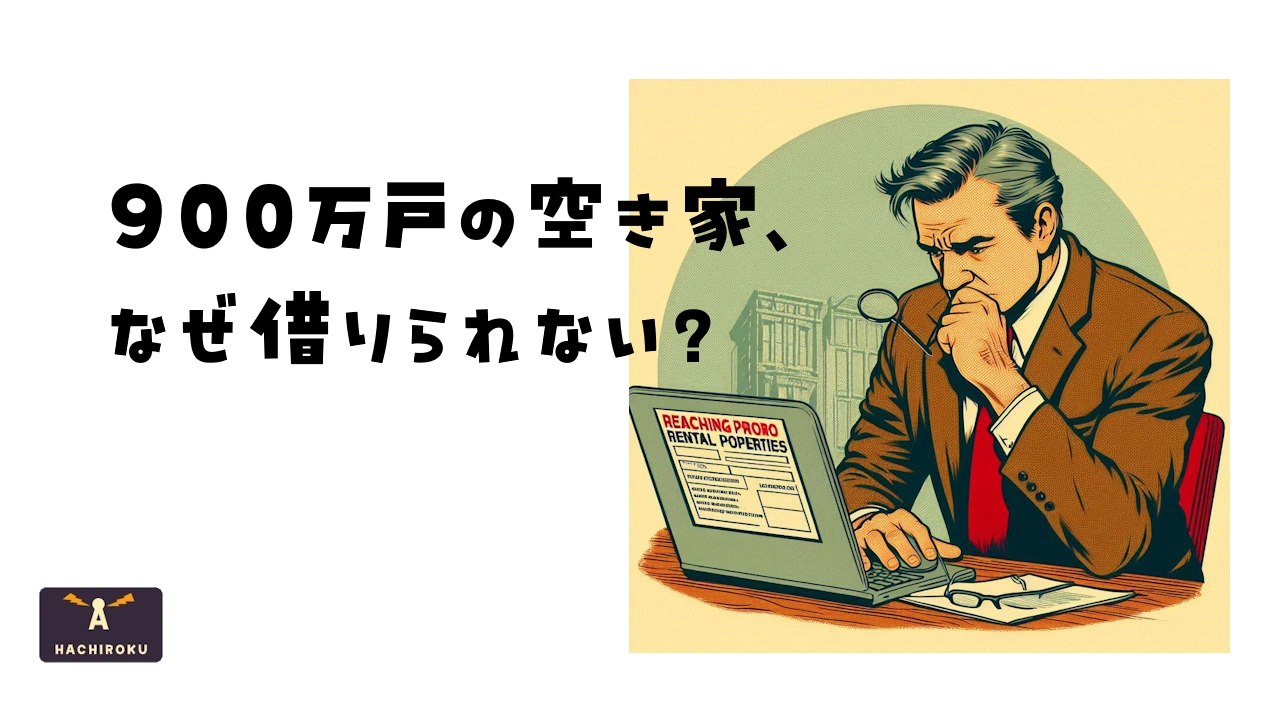
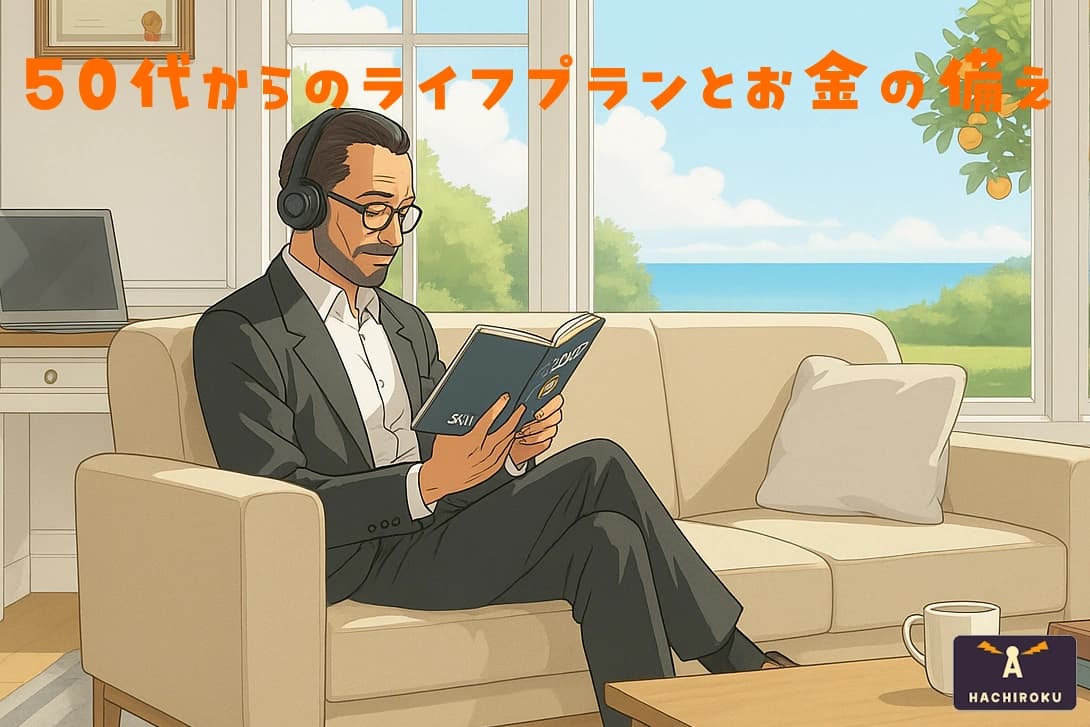


コメント