生活保護より辛い老後?「制度の谷間」が持つ深刻な問題
これまでの連載で、高齢者の住まい探しの厳しさについてお伝えしてきました。真面目に働き、年金や貯金で生活する人ほど、国の制度からこぼれ落ちてしまう現実。
今回は、その中でも特に深刻な「制度の谷間」にいる人々、つまり「生活保護はもらえないが、生活はギリギリ」という層が直面する老後と死後の問題について、ある記事を元に考えてみたいと思います。
制度の谷間が露呈した、ある女性の相談事例
プレジデントオンラインで読んだ記事でこんなものがありました。
書籍の執筆者であり、NPO法人エンディングセンターの代表も務める井上治代さんが書かれた書籍、『おひとりさま時代の死に方』(講談社+α新書)。
井上治代さんはその中で、エンディングセンターに相談に来た女性のこんな事例を紹介しています。
エンディングセンターに近県から相談にやってきた女性がいた。(中略)誰も頼める人がいない。「死後のことを託すといくらぐらいかかりますか」と心配そうに聞いた。
「このくらいはかかります」と話すと、「これからも生活していかなければならないので、お金がありません。(中略)「亡くなられてご遺体の引き取り手がない場合は、ご遺体があった自治体の長が火葬し、お骨を安置した後、無縁塔、無縁塚などと言われるところに納骨してくれます」と最悪の状況を話すと、「それでいいです。安心しました」と言い残して帰って行った。
※引用元:プレジデントオンライン『「生活保護以下」でも「死ねない」おひとりさまの哀れな最期』(2025/9/6、井上治代)
●本記事は、特定の団体やサービスを推奨するものではありません。
夫と離婚し、娘も亡くなり、孤独になった女性。死後のことを託したいが、お金がないか心配している。
「ご遺体の引き取り手がない場合、自治体が火葬し、無縁仏として納骨する」という話を聞き、「それでいいです。安心しました」と言って帰った。
彼女の「安心しました」という言葉は、私たちに何を問いかけているのでしょうか?
なぜ「制度の谷間」が生まれるのか?
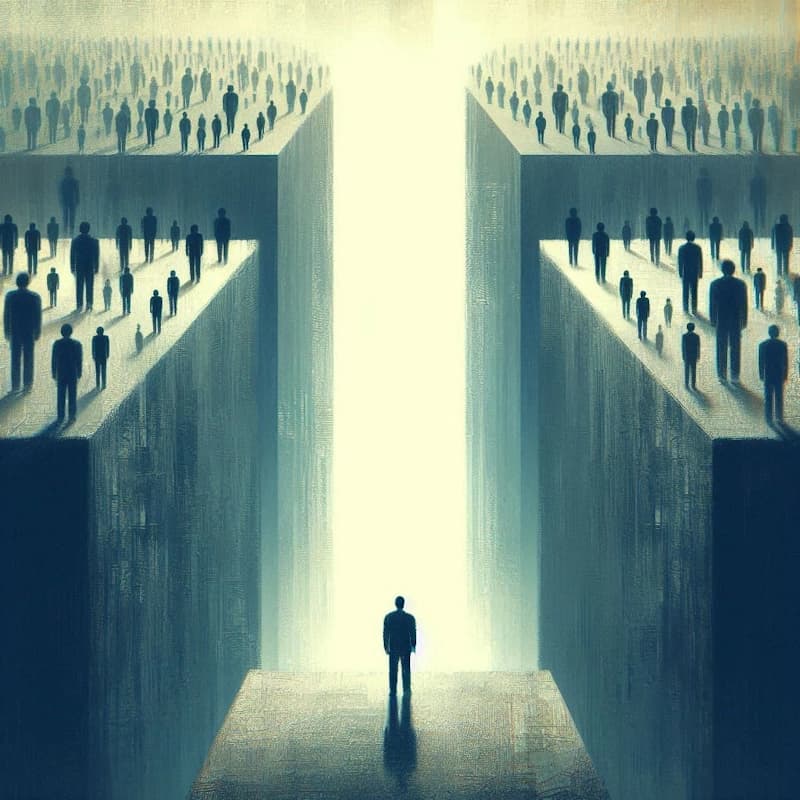
生活保護制度の基準
生活保護は、厚生労働大臣が定める最低生活費を下回る収入の世帯に適用されます。
参考:厚生労働省-生活保護制度
「生活保護の基準額」は全国一律ではありません。実は、私たちの住む地域によって、もらえる金額は細かく変わります。
参考:厚生労働省-最低生活費認定額(pdf)
その基準となるのが、厚生労働省が定める「級地制度」です。
これは、地域の物価や生活水準の差を考慮し、日本全国を1級地(大都市)から3級地(地方)まで6段階に分けて、生活保護費の基準額を決める仕組みです。
例えば、家賃が高い東京23区に住む人と、地方の町村部に住む人では、同じ生活保護を受給しても、もらえる金額に大きな差が出ます。
つまり、「最低限の生活」は、住む場所によって金額が違うのです。
この仕組みがあるからこそ、私たちはこんな矛盾に直面します。
「生活保護の基準額を下回る収入しかないのに、なぜか生活保護は受けられない」

なぜなら、その地域で定められた基準額をわずかでも上回ってしまうと、たとえ生活が苦しくても、制度の対象から外れてしまうからです。
真面目に働いて、税金や社会保険料を納め、その地域の基準額をほんの少し超える収入を得ている人。
彼らは、生活保護も受けられず、公的な葬儀扶助制度も利用できません。最低限の葬儀さえ、自己資金でまかなう必要があるのです。
※葬祭扶助制度: 生活保護受給者が亡くなった場合、葬儀費用を自治体が負担する制度(一般的に20万6,000円以内)
これまで社会を支えてきたはずの真面目な市民や、記事の女性のような方が、最も厳しい「制度の谷間」に置かれる。この現実こそが、私が最も憤りを感じる点なのです。
ハチロクの考察:なぜ「真面目に生きてきた」人ほど苦しむのか?
私は常々疑問に思っていました。なんでこれまで必死で働いて、生きて、そして税金や社会保険料を納めてきた人が、こんなにも大変な思いをしなければならないのか?
社会の「勝ち組」「負け組」なんて誰が勝手に決めた基準だ。
真面目に生きてきた人が、死後も社会の世話にならず、尊厳ある最期を迎えたいと願うこと。それすら叶わないこの社会の仕組みに、私は憤りを感じずにはいられません。
あなたにとっての「幸せな死に方」とは?
「生活保護をもらえないギリギリの生活」が、最も孤独で報われない状況を生み出しています。
あなたは、誰かに頼ることなく、自分らしく最期を迎えたいですか?
それとも、社会の力を借りることに躊躇しますか?
高齢者の住まい探しの厳しさについて、以下の記事を書いています。
まだ私は「準備段階」ですが、自分らしい最期を迎えるためにも今後も有益な情報を発信していきます。
最も読んでいただけている記事がこちらです。
関連記事はこちらです。
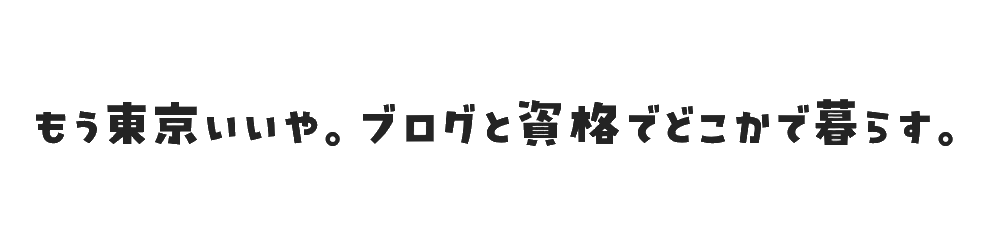
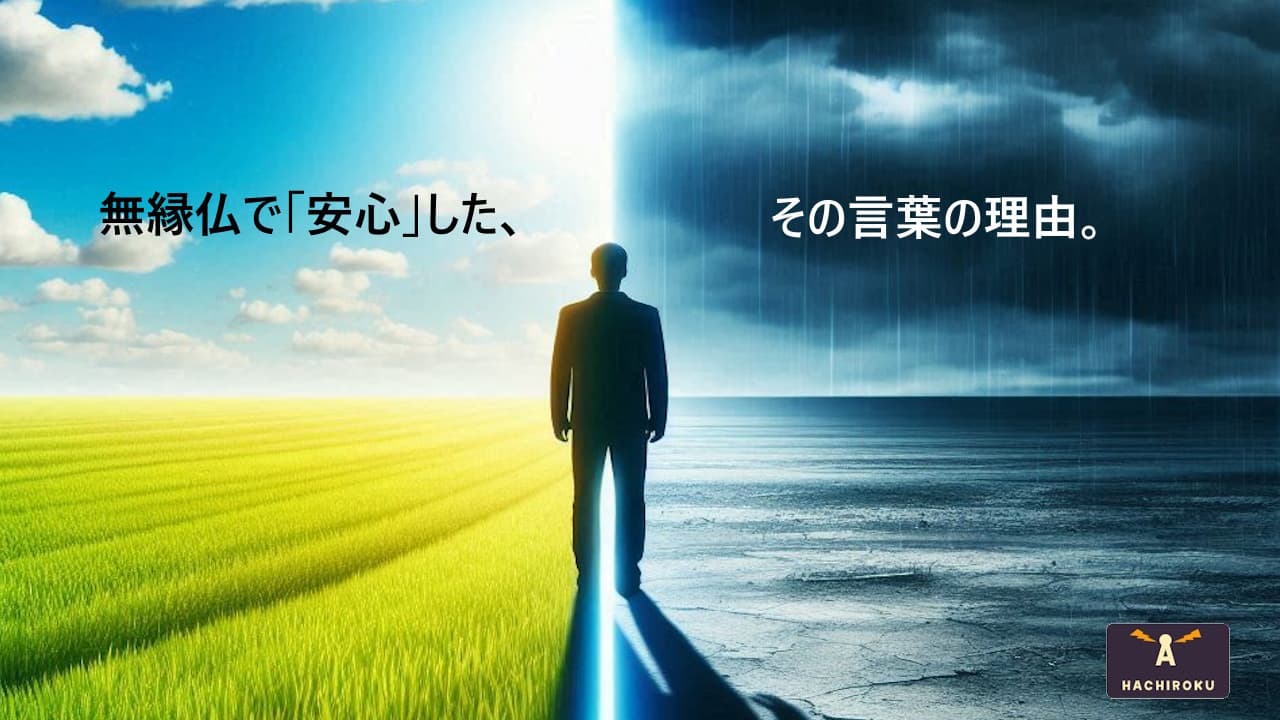

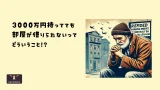
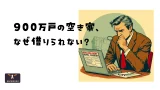
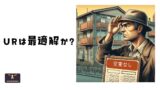


コメント