先日「派遣の三年ルール」の記事を書いたことで、改めて自分の働き方を見つめ直すきっかけになりました。
契約という期限の中で働く現実。その延長線上に、もう一つの働き方を模索し始めました。
派遣で働くことに不満があるわけではありません。
むしろ、柔軟で自分のペースを大切にできる面も多くあります。
ただ来年の4月で一旦終了は確定しています。その後の転職活動や、クーリング期間後の身の振り方を考えるとき、別の柱を持っておきたい。
そんな想いから、少しずつ新しい動きを始めています。
三年ルールで気づいた「自分の軸で動く大切さ」
派遣社員として働く以上、三年ルールは避けて通れません。
同じ職場で働けるのは最長3年。泣いても泣いても(笑えるか!)、また一から環境を作り直す必要があります。
この期限付きの働き方は、言い換えれば常に「リセットの可能性」と隣り合わせです。
スキルを磨いても、真面目に休まず働いても、そして、長く続けたいと思っても制度的に不可能な現実。
この構造を改めて考えると、「働く」ということを制度の外側から見つめる必要があると感じました。

いくら頑張っても、自分の力の及ぶ範囲ではどうにもならないことに振り回されることほど、腹立たしいことはありません。
このブログの他のカテゴリーでも取り上げている、高齢者の住まいの問題も同じです。
中高年の派遣社員にとって「3年ルール」は、無職への片道切符。
副業は「逃げ」ではなく「実験」
そこで考えたのが、副業という選択肢です。
ただし、私にとっての副業は逃げ道ではありません。
今の仕事を辞めるためではなく、「働き方を広げる実験」としての副業です。
もともと学ぶことや発信することが好きだったので、YouTubeで文化系の動画を作ったり、このブログで学び直しの記録を書いたりと、少しずつ形にしてきました。
最初から収益を狙うというよりも、「自分の経験を残す」「表現を続ける」という感覚です。
完成度よりも、続けられること。
それが今の自分にできる、最初の一歩だと思っています。

凝り性なわたしは動画作りで何度も何度もつまずいてます。それはブログも同じかもしれません。
とにかく公開する、記事を書きあげる。
それがなかなかできないのです。中途半端でいいのだろうか?もう少し巧く表現したい。
そんなことで逡巡しているとペースが落ちて結局モチベーションも下がってしまいます。今の課題はここです。
小さな一歩として始めたこと
動画制作では、文化をテーマにしたチャンネル「和心」を立ち上げました。
日本の神社やお寺、季節の行事などを、海外の人にも分かりやすく伝える内容です。
動画編集ツールや字幕の設定など、手探りながらも一歩ずつ進めています。
これもまた、「働く形の延長線上にある副業」です。
時間を切り売りする仕事ではなく、自分の知識や関心を少しずつ形にしていく。
それが、未来の働き方の練習になっていると感じます。
もう一つの可能性──「日本語教師」という選択肢
もう一つ、最近気になっているのが「日本語教師」という資格です。
副業というよりは、学びながら働く新しい選択肢かもしれません。
外国人支援や教育の分野で需要が高まり、国家資格にもなりました。
今後、日本の高齢化と人口減少で確実に外国人の労働者に頼らざるを得ない日がくると思います。
このブログではあまり政治的な話にはしたくありませんが、わたしが「日本の文化」チャンネルを立ち上げたのも、何とかうまく共存の道が開けないだろうか?と言う思いがありました。
技能実習生の制度が大きく変わりました。まだまだ問題は山積みだとは思いますが、今後日本で働こうとする外国人の方に求められる「日本語スキル」は、これまで以上に難易度が上がります。
このような世情から「日本語教師」の需要が見込まれるというわけです。
年齢を重ねても続けられる仕事であり、オンラインでの副業も可能。
シニア世代にはもってこいではないでしょうか?
制度や年齢に左右される働き方は気持ちも疲弊します。自分軸で動けないからです。
すぐに形にできるとは思いませんが、次の軸として自分で収入を得られる資格取得を準備していくのも現実的な目標だと思っています。
MOSの学習を通じて得た「勉強の習慣」や「続ける力」を活かして、自分の働き方をもう少し広くする、そんな感覚です。

単純な私が後で気づいて大きく凹んでいること。それは「日本語教師」と言うことは相手は外国人。つまり、少なくとも英語で会話をする必要が!なんてこった・・・。考えてなかったです(笑)まずは自分の英語スキルじゃないですか・・・・・・。
今の段階で感じること
副業や資格取得の準備は、すぐに結果が出るものではありません。
でも、行動してみて分かったのは、「働き方は一つではない」ということ。
派遣や契約という枠組みの中にいても、自分の意思で学び、発信し、新しい選択肢を作っていくことはできる。
その一歩が、将来の安心や自信につながるのではないでしょうか。
焦らず、でも確実に。
未来の自分が安心して選べるように、今の自分が小さな実験を続けていきます。
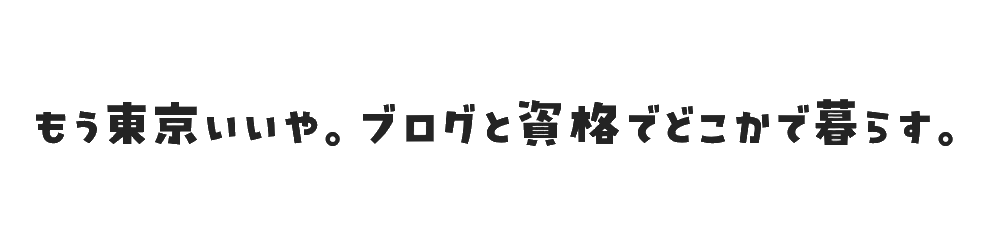
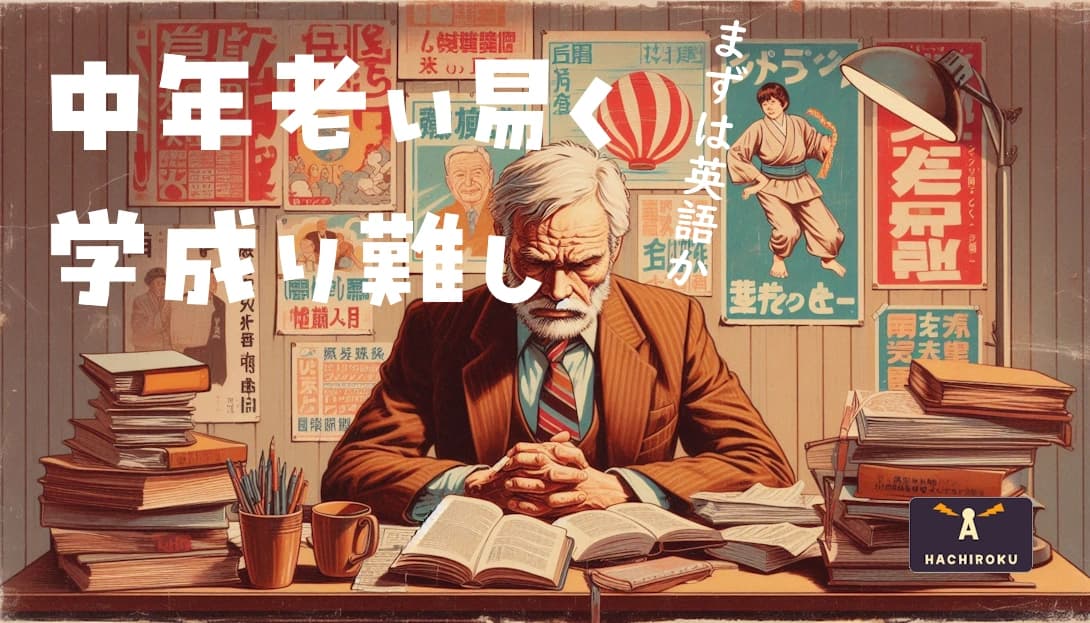


コメント