老いは「終わり」ではなく、「もう一度、始まり」だ。
noteで妄想した“じじばば共和国”。
笑い話のようで、実は日本の現実にこそ必要な構想なのかもしれません。
note版エッセイ:「ゲートボールより自治を!“じじばば共和国”構想」
高齢者が「制度の谷間」に落ちていく現実
2025年、日本の65歳以上人口は3,800万人を超えます。
つまり国民の3人に1人が高齢者。
しかし、一人暮らしの高齢者が「住まい」を失うケースが急増しています。
「高齢単身者お断り」
「保証人がいないと入居できない」
「見守りサービスが必須で家賃が高い」
制度が整っているように見えても、現場では選別が行われているのが実情です。
居住支援法人やセーフティネット住宅制度もありますが、利用できる地域は都市部に偏り、地方ではほぼ機能していません。
「じじばば共和国」が示すのは、“自助”と“共助”の再構築
noteで描いた理想郷~「医者も大工も電気工事士もいる、高齢者だけの自立型コミュニティ」。
笑い話のようですが、実はこのモデル、現行制度が抱える課題を埋める現実的ヒントを含んでいます。
ポイントは3つです。
1️⃣ スキルと経験を再配分する仕組み
年齢ではなく「できること」で役割を担う社会。
→ 地域版「シルバー人材センター」の拡張型に近い。
2️⃣ 行政依存ではなく、相互扶助の仕組み
→ 小さな単位での自治、互助、共同購入、見守り。
3️⃣ 外部との連携による経済循環
→ 観光、教育、漁業・農業体験、メディア発信などで収益化も可能。
つまり、「高齢者=支えられる側」という構図を逆転させる構想です。
じじばば共和国は、冗談ではなく「自助×共助の再定義」なんです。
問題は「誰を受け入れるか」という線引き
とはいえ、理想のコミュニティにも現実的な課題があります。
・非協力的な人をどう扱うか
・医療・介護などの公共支援をどこまで自前で担えるか
・孤立や内部衝突をどう防ぐか
このあたりはまさに「小さな国家の政治」です。
自由と秩序、受け入れと排除、理想と現実のバランス。
おそらく、ここから再びルールや法が生まれていく。
人間社会の原点を見るような試みになるでしょう。
現実への橋渡し:制度とテクノロジーの融合で実現できる
実際、国も「地域共生社会」「コミュニティ・ケア」を政策に掲げています。
さらにAIや自動運転、遠隔診療などの技術も、高齢者が自立して暮らす社会を支える力になりつつあります。
「じじばば共和国」を笑わずに構想できる時代が、すでに始まっているのかもしれません。
「老い」は守られるだけの時代じゃない
ゲートボールより自治を。
支えられるだけの老後ではなく、もう一度、社会をつくる側に回る老後を。
「じじばば共和国」は、空想ではなく、これからの日本が目指すべき小さな未来の実験場になるかもしれませんね。
老後の生き方模索中
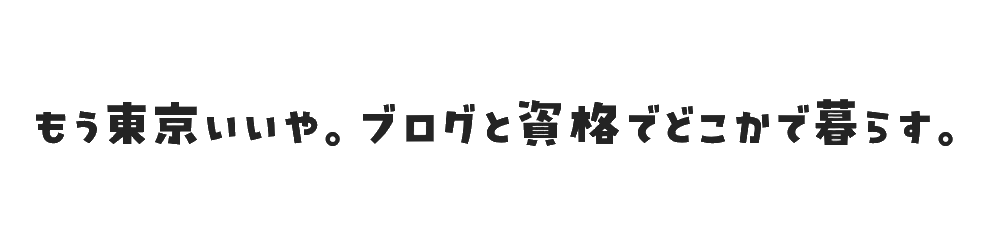

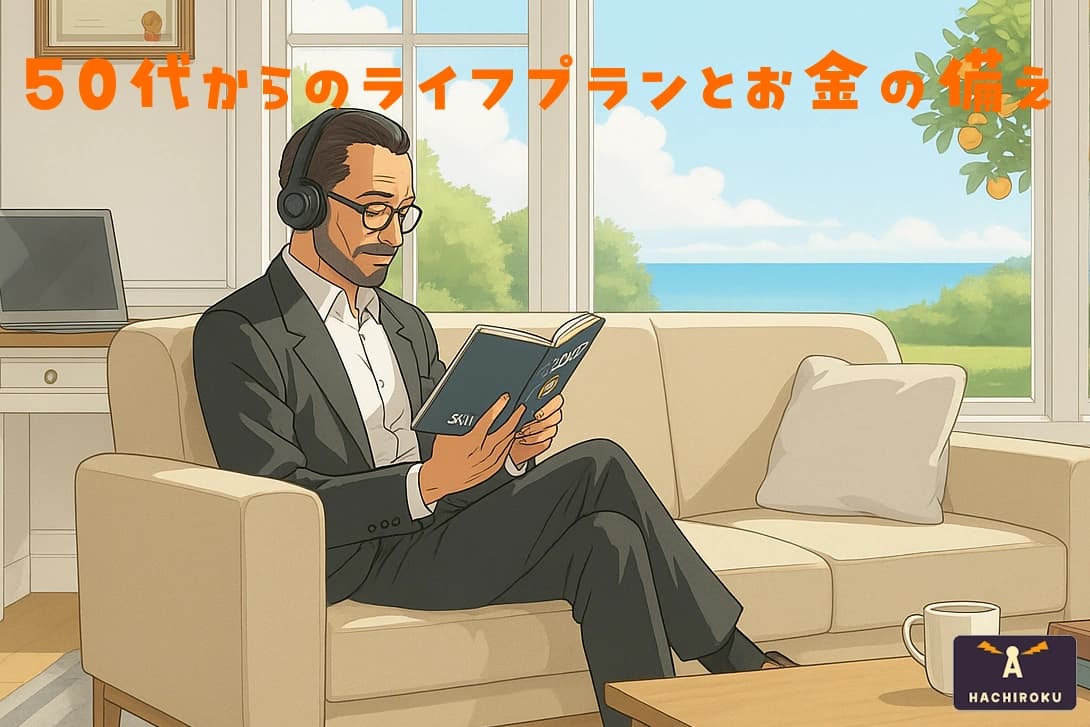
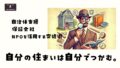

コメント