はじめに:新たな壁、そして「先走り模擬試験」の衝撃
MOS Excel 365 エキスパート試験の独学も第9週目。先週の「模擬試験での惨敗」を受けて、「魔の第三章克服週間」を終えたばかりですが、今週もまた新たな壁に直面しました。
少し焦る気持ちもあり、「よし、この勢いで模擬試験をもう一度!」と意気込んでみたものの、そこで私を待ち受けていたのは、またしても「テキストに載ってない!」「こんな操作、初めて見る!」という驚きの連続でした。
特に、グラフ作成(まさかのパレート図!)に関する問題では完全に思考停止状態に…。さらに、まだ学習していなかったピボットグラフまで出題され、「これはヤバい!」と頭を抱えました。
このままではまずい!と判断し、一度立ち止まって、落ち着いて第4章の「グラフ作成」(ピボットグラフ以外)を進めることに。学習していない機能が出題されるのは当たり前ですが、その衝撃は想像以上でした(笑)
今回は、この「先走り模擬試験」で直面した「テキストだけでは通用しないグラフやピボットテーブルの壁」。そして、そこから見えてきたMOSエキスパート試験の奥深さと、合格を掴み取るための「応用力養成」に向けた具体的な学習アプローチを、私のリアルな体験を交えてご紹介します。
先週の記録はこちら
MOS Excel エキスパート独学記 #8 | 試験は甘くない!「テキスト丸暗記」が通用しない現実と応用力養成戦略
📅 学習期間:7月7日〜7月13日
🎯 今週の目標:第4章1の学習と、模擬試験
📊 1週間の学習記録(第4章1の学習と、模擬試験)
| 日付 | 内容 | 所要時間 | メモ・感想 |
| 7/7(月) | 魔の第三章克服週間の復習 | 50分 | ・先週の「関数が思い出せない病」対策を継続。関数とキーワードの紐付けは少しずつ定着。 |
| 7/8(火) | 「先走り模擬試験」に再挑戦(再び衝撃) | 50分 | ・意気揚々と模擬試験を始めたものの、グラフ作成(特にパレート図!)で「???」連発!さらに未学習のピボットグラフまで登場し、完全に混乱。 |
| 7/9(水) | 第4-1「グラフを作成する」学習 | 60分 | ・焦って模擬試験を続けるのは非効率と判断し、基礎に立ち返る。テキストのグラフ作成(ピボットグラフ以外)を丁寧に学ぶ。ここでパレート図の場所を確認。 |
| 7/10(木) | グラフ作成の応用演習 | 60分 | ・棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど基本に加えて、複合グラフを学ぶが・・・関数と同じでどこでどのグラフを使うかが難題。 |
| 7/11(金) | 模擬試験の該当範囲を再挑戦 | 25分 | ・第4-1学習後、再度模擬試験のグラフ関連問題に挑戦。パレート図など一般グラフは解けるようになったが、未学習のピボットグラフはやはり手が出ず。 |
| 7/12(土) | 模擬試験全体の再分析 | 60分 | ・模擬試験が「テキストの穴」を教えてくれる最高の教材だと再認識。 |
| 7/13(日) | 時間制限付きで模擬試験を繰り返す | 75分 | ・本番と同じ環境での模擬試験。アソシエイトもこうやっていたことを思い出した。 |
【完全解説】MOSエキスパート必須!グラフの選び方と正しい使い分け
MOSエキスパート試験の出題範囲には、「グラフの作成とカスタマイズ」が含まれています。中でもつまずきやすいのが、「どのグラフを使えばいいのか分からない」という問題。
目的に応じたグラフの使い分けと、項目名(ラベル)の扱い方についてまとめてみました。
グラフの選び方は「伝えたいこと」で決まる
MOSエキスパート試験では、棒グラフや円グラフといった基本的なグラフだけでなく、データ分析やビジネス報告に使われる高度なグラフの作成・編集も出題されます。
以下に、テキストに登場する7種類のグラフについて、「いつ・どんな場面で使うのか」「どんな特徴があるのか」を実務目線でまとめました。
MOS試験に出る!高度なグラフ7選(使い方とポイント)
- 2軸グラフ(複合グラフ)
- ヒストグラム
- パレート図
- 箱ひげ図
- サンバースト
- じょうごグラフ(ファネルチャート)
- ウォーターフォール図
MOSエキスパート試験対策!各グラフの「実践的な使い方とコツ」
1. 2軸グラフ(複合グラフ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 用途 | 異なる単位・スケールのデータを比較したいとき(例:売上と利益率) |
| 📊 特徴 | 第2軸を使い、折れ線と棒などを組み合わせる |
| 📝 ポイント | 「グラフの種類の変更」から系列ごとに設定。凡例と軸の区別を意識 |
2. ヒストグラム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 用途 | データの「分布」や「ばらつき」を見たいとき(例:テスト点数の分布) |
| 📊 特徴 | 数値の範囲ごとの頻度を表現。カテゴリではなく「区間」軸 |
| 📝 ポイント | データ分析系に必須。分類の幅(ビン)を調整して見やすく |
3. パレート図
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 用途 | 「重要な要因は何か」を分析したいとき(例:クレームの原因分析) |
| 📊 特徴 | 左軸の棒(頻度)+右軸の折れ線(累積比率) |
| 📝 ポイント | 棒グラフは高い順に並べる。折れ線の80%を目安に改善対象を絞る |
4. 箱ひげ図(ボックスプロット)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 用途 | データのばらつきや外れ値を確認したいとき |
| 📊 特徴 | 四分位数・中央値・最小最大をまとめて視覚化 |
| 📝 ポイント | 外れ値を示す点が表示される。ヒストグラムとの違いを理解 |
5. サンバースト(同心円グラフ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 用途 | 階層構造(部門→課→担当者など)を可視化 |
| 📊 特徴 | 円の中心から外へ階層を展開。割合も確認できる |
| 📝 ポイント | 多階層データの全体像を把握しやすい。ツリーマップと使い分け |
6. じょうごグラフ(ファネルチャート)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 用途 | プロセスごとの減少を可視化(例:サイト訪問→申込まで) |
| 📊 特徴 | 上から下へ向かって数が減る形状。段階ごとの離脱率が明確 |
| 📝 ポイント | マーケティングで頻出。段階名と数値ラベルの表示に注意 |
7. ウォーターフォール図
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 用途 | 数値の増減の内訳を視覚化(例:売上→経費→最終利益) |
| 📊 特徴 | 増加・減少の推移を棒で積み上げる構成 |
| 📝 ポイント | 開始→変化→終了、という流れを意識。色分けで変化を強調 |
グラフを選ぶときの視点:目的別早見表
| 見たい情報の種類 | 適したグラフ |
|---|---|
| 異なる単位を比較 | 2軸グラフ(複合グラフ) |
| 分布・ばらつき | ヒストグラム、箱ひげ図 |
| 原因の重要度 | パレート図 |
| 階層構造の分析 | サンバースト |
| プロセスの離脱率 | じょうごグラフ |
| 増減の内訳 | ウォーターフォール図 |
まとめ:実務でも役立つ「高度なグラフ」
これらの高度なグラフは、MOS試験のためだけでなく、実際の仕事でもデータ分析・資料作成に大きく役立ちます。
ポイントは、「どのグラフがどんな目的に向いているか」をパターンで覚えておくこと。
実際にExcelでデータを使って練習すれば、操作方法とあわせて理解が深まります。
【体験談】MOSエキスパート模擬試験の「応用問題」が意地悪すぎる!
わたしの「先走り模擬試験」と、それに続く第4-1のグラフ学習で、MOSエキスパート試験の「巧妙な罠」と、それに対する「真の対策」が見えてきました。
- 「死角」に潜む重要機能:
- パレート図のように、日常的に使わない、あるいはテキストの隅っこにしか載っていない機能が、平然と出題されることがあります。これは、「テキストの全てに目を通し、どこに何があるかを知っているか」を試されているのだと理解しました。意地悪ですよね(笑)
- 「グラフは奥が深い」:単なる見た目ではない応用力:
- 棒グラフや円グラフの作成自体は簡単ですが、模擬試験では「特定のデータ系列を強調」「複合グラフの軸設定」「トレンドラインの追加と表示オプション」など、一歩踏み込んだ応用操作が求められます。これは、単にグラフを作るだけでなく、データを「いかに効果的に見せるか」という視点が問われている気がします。
- 「焦らず、立ち止まる勇気」の重要性:
- 知らない問題に直面したとき、焦って闇雲に解き続けるよりも、一度学習に戻り、基礎から応用までを丁寧に学び直すことの重要性を痛感しました。結果として、グラフ作成(ピボットグラフ以外)の問題は、前回よりも格段に解けるようになりました。
処方箋:模擬試験を「最強の教材」にする応用力養成戦略
今回の経験を通じて、今後の学習戦略をさらに強化することにしました。
- 【最重要】模擬試験を「知らないことを知る」ための教材にする:
- 模擬試験は、「自分の知識の穴を可視化してくれるドリル」です。知らないワードや操作が出てきたら、それをチャンスと捉え、テキストに戻って該当箇所を徹底的に調べる、あるいは公式ヘルプなどを活用して深掘りします。
- 特に「こんなこと習ってない!」と感じた部分こそ、重点的に時間をかけて理解し、手を動かして習得します。
- 各機能の「詳細オプション」を探索する:
- グラフに限らず、これまで学習した各機能について、「右クリックメニュー」や「リボンの詳細設定」など、「普段あまり触らないけど、実は色々なオプションがある場所」を意識的に探索してみます。ここに、模擬試験で問われるような応用機能が隠されていることが多いです。
- 「なぜ?」を常に問う学習:
- 単に操作手順を覚えるだけでなく、「なぜこの機能が必要なのか」「どんな時に使うのか」「他の似た機能との違いは何か」という「なぜ?」を常に自問自答し、本質的な理解を深めます。
📚 私のMOS Excelエキスパート学習方法(最新版)
週を重ねるごとに、少しずつ学習方法も変わってきています。
これまでの学習方法に加えて加筆していきますので、過去投稿と同じ部分もありますがご参考までにどうぞ。
1. 朝のインプット:テキストで確認と動画視聴
朝、まずは「FOM出版 よくわかるマスター」のテキストで今日学ぶ「章-節」を改めて確認します。
どんな関数を学ぶのか?どんな機能を学ぶのか?など、その日の学習範囲を把握します。
私がお世話になっている動画はこちら
朝夕の通勤電車の中で、YouTube動画を見ます。
MOSExcelエキスパートの動画は、アソシエイトに比べると本当に少なくて残念なのですが、私は、「オンラインパソコンスクール♥キャリアデザイン」さんの「MOSエクセルエキスパート出題範囲完全網羅講座/Excel2019【データ無料】」を主軸に見ています。
ただ、こちらの動画は動画名からもわかる通り「Excel2019」編なので、私が受けようとしている「Excel365」とは範囲が若干異なります。
その場合は、個別で解説をしてくれている動画を見て補完学習しています。
2. 注目のYouTubeチャンネル:ExcelドカタCHさんと、じゃぱそんさん
特にExcelドカタCHさんの解説動画はとても分かりやすくてオススメです。「Excel職人」の筆字が渋い!
来週学習予定の「ピポットテーブル」についてわかりやすい動画を上げてくれています。
ピボットテーブルを使うなら、最初にこの基本ルールを理解しましょう【Excel】

Excel動画解説には人それぞれ特徴があって、視聴者の方も自分に合う動画、合わない動画があると思います。なのでほかの動画を批判するようなことはしませんが、私的にはこの「ExcelドカタCH」さんの解説が一番わかりやすいです。お世話になります。
試験対策のアドバイスが満載のアソシエイトの試験勉強でお世話になった「じゃぱそん」さんのYouTube動画。
今回学んだ「グラフ」の動画はこちら。じゃぱそんさん、相変わらず声が小さい(笑)
MOSExcelExpert4章:高度な機能を利用したグラフやテーブルの管理
じゃぱそんさんは、「試験に特化」したポイントをたくさん教えてくれます。私はもちろん合格はしたいですが、同時に業務でもしっかり使いたいので、時間を出来るだけかけて学ぶように心がけていますが、MOS試験はとても癖があるので、じゃぱそんさんのアドバイスやポイントは非常に役立ちます。

じゃぱそんさんの動画は音声が小さめです。なのでこの動画を見ている途中に入るCMや、別の動画に切り替えた時に、同じ音量のままだとびっくりする音量が流れるので注意(笑)
3. 夜のアウトプット:テキストと問題演習、AI活用
家に帰ったら、YouTube動画で見た範囲をテキストを使って勉強して、問題を必ず解きます。
そこですんなり解けなかったり、納得できないところがあったらAIに問題を作ってもらって解きながら勉強しています。
AIに問題を作ってもらう方法は、こちらの記事で詳しく書いています。
使うAIによって個性が出ていて面白いですよ。
MOS Excel エキスパート独学記 #3 | AI活用で効率復習!XLOOKUP関数の問題演習とAI比較
4.模擬試験プログラムの徹底活用
模擬試験を解く日を作り、ランダムな問題にチャレンジすることで少しでも多くの問題と、問題文の癖や傾向に慣れるようにします。
💡 今週の気づきと今後の課題
「先走り模擬試験」で新たな壁にぶつかり、正直焦りは増しました。しかし、そのおかげで、グラフ作成の奥深さや、MOSエキスパート試験の「応用力」を試す意図を肌で感じることができました。これは、本番で合格するための、非常に貴重な経験です。
残された時間で、この「知らなかったこと」を一つずつ潰し、各機能の「応用」と「詳細オプション」まで視野に入れた学習を徹底していきます。特に、後回しにしたピボットグラフは、来週の最優先課題として取り組む予定です。
📝 今週のまとめと次週への抱負
模擬試験は、私の学習の甘さを教えてくれる厳しい先生ですが、同時に「合格への最短ルート」を示してくれる頼もしい味方でもあります。
今週の「グラフの落とし穴」をきっかけに、「テキスト通りだけでは通用しない」という現実を再認識し、より実践的な学習へとシフトする決意を固めました。この「知らなかった」という焦りを、「できる」に変えるべく、試験本番まで全力を尽くします!
来週は、なんでこの関門が最後に!?の「ピポットテーブル」の章を勉強します。
アソシエイトではまったく触れなかった「ピポットテーブル」。これを残したままでは、非常にまずい。関数以外のポイントはまさにここ。気合い入れます。
片っ端から忘れる病のために、模擬試験も続けて解きつつ学習をしていこうと思います。

この学習スケジュールは毎週末に一週間の記録として連載していきます。
では、また来週。
📣 X(旧Twitter)もやってます!
勉強の進捗や日々の気づきなどを、Xでも発信していきます📣
#MOS試験 #Excel独学 で検索していただくか、ぜひフォローしてお気軽にご覧ください!
フォローはお気軽にどうぞ! → @hachiroku_lab
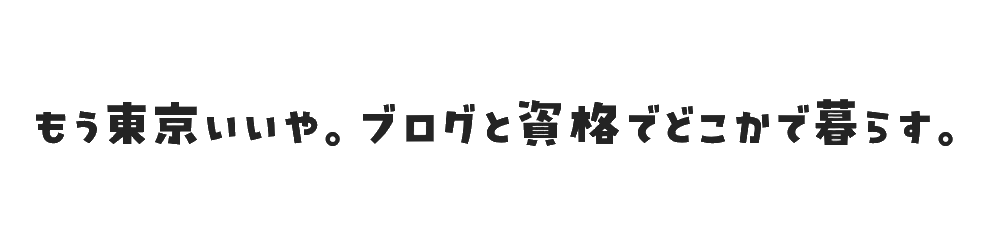
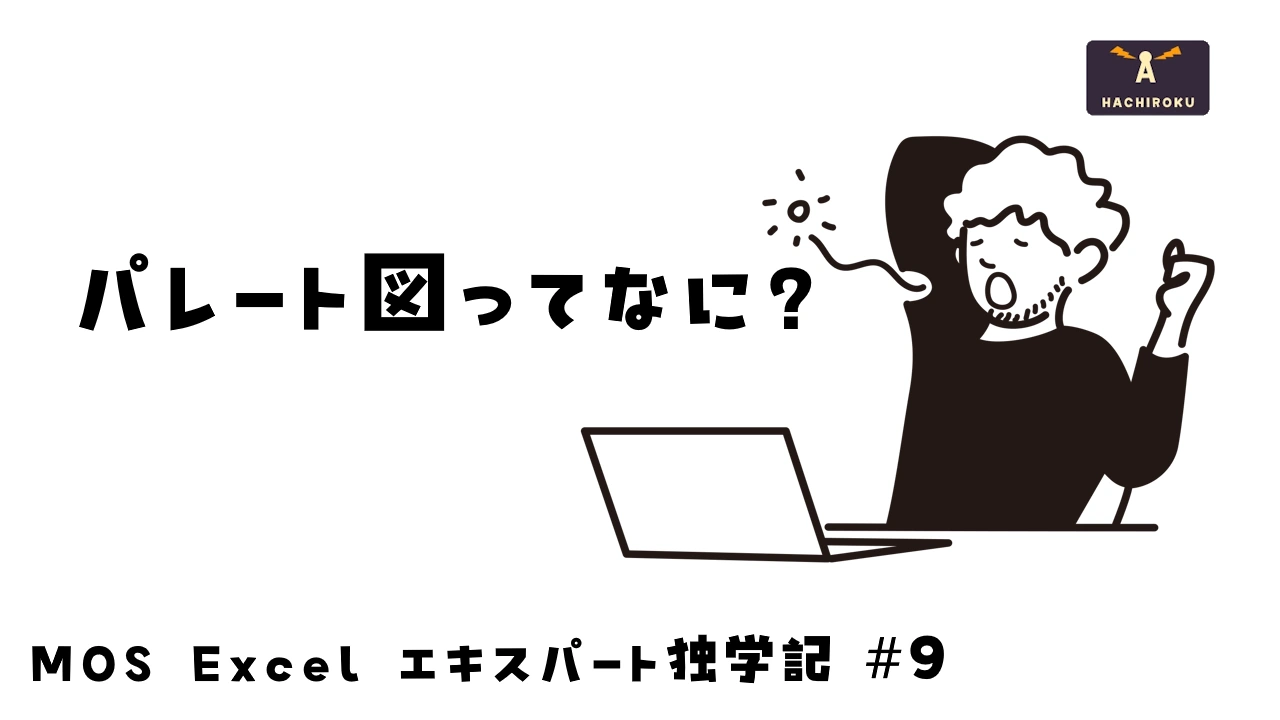



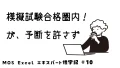
コメント